スープという信頼 ― 2023年05月01日 19:20

以前に日本語学習を支援した元留学生の引越先へ昼食の招待を受けて行ってきました。久しぶりの対面の再開で母国風ランチをご馳走になり、持参したコーヒーを淹れてもらって飲みながら、いろいろな会話を楽しむことができました。
その中で、話題になったことの一つが臨場感です。無料チケットで観戦したVリーグの試合が、テレビ中継とは違う現場の高揚感に溢れていたそうです。フルセットの1点を争う試合展開もさることながら、観客に対する鑑賞制限が少なくなってきたこともあって、何より“その場”に臨んでいる身体が、環境に大きく反応したのでしょう。
ライブということでは、能・狂言の舞台も同様です。ただし、そこには熱狂的な応援ではなく慰霊につながる空気が充満している違いがあります。事前に詞章をしっかり読んで理解した上で見所に赴くのは、いざ舞台が始まったら、演目の内容理解以上に“その場”に立ち会っていることを体感したいからだと思うのです。意味のわからない言葉を聞き取ろうとする営為が、身体を置いている“その場”の感覚そのものを鈍らせるような気がします。あの没入感覚が生まれなければ能・狂言の面白さは半減するはずです。
能や歌舞伎などの伝統芸能に限らず、演劇一般の映像が記録・公開される時、なぜ劇場全体を俯瞰した映像を独立して出さないのでしょうか。その場にいれば目の“端”に映る舞台の“隅”の様子や、見所全体の“雰囲気”を想像できるはずなのです。それは、スポーツ中継などでも同様だと思いますが、カメラスイッチングや編集を行う人間の個性によって切り取られた映像だけを見せられることに多くの人は慣れてしまっています。映像記録の高密度化が進んだ頃、8chビデオのようなものが夢見られました。編集者の目で切り刻まれる前の多ch素材を自らが選ぶことができることへの要望です。しかし、それは実現しませんでした。なぜならば、いくら高精細度で多chの映像や高臨場感の音響があったとしても、それは“その場”ではないからです。
関連して思い出したことが一つありました。くだんの留学生の日本語論文をチェックしていた時のことです。アニメーションによるドキュメンタリーを考える論考の中で、映像記録という行為が被写体に影響を与えることを説明する的確な表現がなかなか見つかりませんでした。後刻、ようやく思い浮かんだのは「可塑性」という言葉です。カメラによって日常に介入した行為が、その被写体に何らかの波紋を投ずることを表したつもりです。
不正確な情報を含む膨大なテキストデータから、いかにもな応えを差し出してくるChatGPTのようなものに頼らず、意味を含めた言葉の表現を考えだした時のことは今も忘れられません。その時のメールの遣り取りは自戒をこめて、これからも残しておきます。同時に、映像が現実のほんの一部しか切り取っていないことをメディアリテラシーの基本として考えることも、これからの時代には必要でしょう。身の回りに溢れる情報がフェイクだらけという未来はもう目の前に来ています。
もしかしたら、一緒に食べる手作りのスープの中にこそ、本当の“信頼”があるのかもしれません。
その中で、話題になったことの一つが臨場感です。無料チケットで観戦したVリーグの試合が、テレビ中継とは違う現場の高揚感に溢れていたそうです。フルセットの1点を争う試合展開もさることながら、観客に対する鑑賞制限が少なくなってきたこともあって、何より“その場”に臨んでいる身体が、環境に大きく反応したのでしょう。
ライブということでは、能・狂言の舞台も同様です。ただし、そこには熱狂的な応援ではなく慰霊につながる空気が充満している違いがあります。事前に詞章をしっかり読んで理解した上で見所に赴くのは、いざ舞台が始まったら、演目の内容理解以上に“その場”に立ち会っていることを体感したいからだと思うのです。意味のわからない言葉を聞き取ろうとする営為が、身体を置いている“その場”の感覚そのものを鈍らせるような気がします。あの没入感覚が生まれなければ能・狂言の面白さは半減するはずです。
能や歌舞伎などの伝統芸能に限らず、演劇一般の映像が記録・公開される時、なぜ劇場全体を俯瞰した映像を独立して出さないのでしょうか。その場にいれば目の“端”に映る舞台の“隅”の様子や、見所全体の“雰囲気”を想像できるはずなのです。それは、スポーツ中継などでも同様だと思いますが、カメラスイッチングや編集を行う人間の個性によって切り取られた映像だけを見せられることに多くの人は慣れてしまっています。映像記録の高密度化が進んだ頃、8chビデオのようなものが夢見られました。編集者の目で切り刻まれる前の多ch素材を自らが選ぶことができることへの要望です。しかし、それは実現しませんでした。なぜならば、いくら高精細度で多chの映像や高臨場感の音響があったとしても、それは“その場”ではないからです。
関連して思い出したことが一つありました。くだんの留学生の日本語論文をチェックしていた時のことです。アニメーションによるドキュメンタリーを考える論考の中で、映像記録という行為が被写体に影響を与えることを説明する的確な表現がなかなか見つかりませんでした。後刻、ようやく思い浮かんだのは「可塑性」という言葉です。カメラによって日常に介入した行為が、その被写体に何らかの波紋を投ずることを表したつもりです。
不正確な情報を含む膨大なテキストデータから、いかにもな応えを差し出してくるChatGPTのようなものに頼らず、意味を含めた言葉の表現を考えだした時のことは今も忘れられません。その時のメールの遣り取りは自戒をこめて、これからも残しておきます。同時に、映像が現実のほんの一部しか切り取っていないことをメディアリテラシーの基本として考えることも、これからの時代には必要でしょう。身の回りに溢れる情報がフェイクだらけという未来はもう目の前に来ています。
もしかしたら、一緒に食べる手作りのスープの中にこそ、本当の“信頼”があるのかもしれません。
沢崎が逝く ― 2023年05月13日 19:24
ハードボイルド小説の世界で寡作として知られた、作家原尞が亡くなったそうです。5年前の作品が最後になりました。探偵沢崎の少し老いた姿はどんなものになるのか。これで本当に次作が読めなくなりました。合掌。
しあわせのようなもの ― 2023年05月16日 19:26

GWが終わって初めての日曜日。一昨日、雨模様の中を外出してきました。訪ねたのは栄区本郷台「あーすぷらざ」の5階にある映像ホールです。“ごちゃまぜ”と称して続けている伊勢監督の映画会は、今年はちょっと特別なものになりました。「長くは生きられない…」と医者に言われた実の姪「奈緒ちゃん」を撮り続けて30年近く。伊勢さんは、今年50歳になる奈緒ちゃんの「いのち」の記憶をまとめるべく、次回作の上映・制作支援を呼びかけています。今回の映画会もその一環ですが、取り上げられたのは最新作『PascaLs』と旧作『ゆめみたか』という音楽をテーマにした二作でした。
午前中の『ゆめみたか』は今年1月に亡くなった田川律氏を追った2008年公開のドキュメンタリー。音楽評論家で晶文社が出した音楽本の翻訳者としても何度か目にした名前ですが、近年は“歌手”として様々なイベントに関わっていたようで、ひょんな出会いから追い続けることになった伊勢さんの撮った映像が、本人のひょうひょうとした個性と相俟(あいま)って何とも“ゆるやか”な作品に仕上がっています。1980年代に水牛楽団の高橋悠治氏らと共にその名をよく見かけましたが、昭和一ケタ(直後)世代の一人として戦後のサブカルチャー、特に音楽シーンに深く関わった豊富な経験の中には「替え歌」もありました。時代や社会を批評する精神から生まれた「替え歌」を諳んじる姿は、軍歌一色に染められた幼き時代へのアンチテーゼのようでもあり、寺の息子の音楽法話のようにも感じられました。何というか“自由”な雰囲気をまとった人というイメージです。
午後の『PascaLs』は、大編成のアコースティックバンド「パスカルズ」のライブ映像を中心とした構成。こちらは3年前に急逝したチェロの三木黃太氏が抜けて現在は13人。「パスカルズ」の名前だけはどこかで聞いた記憶がありましたが、あのイカ天キング「たま」の知久・石川両氏もメンバーです。そして、もう一人。大倉山駅近くにあった喫茶店「カフェ・グランデ」で生の演奏を聴いたことがあるチェロの坂本弘道氏も参加しています。鋸パフォーマンスも健在でしたが、僚友三木氏が抜けた後だけに、20年前の“はちゃめちゃさ”は薄れているように感じました。それは、チラシにもある「不在という在り方」という言葉通り、三木氏が演奏していたであろう場所の頭上に置かれた白い貝の輪と飛び立つ鳥のオブジェが、楽器を演奏している飛天につながるように見えたことと関係があるのかもしれません。ある人は彼らの音楽に多幸感を感じるそうです。天上の音楽ではありませんが、ライブはきっと映画の副題「しあわせのようなもの」みたいな不思議な空間なのでしょう。
午前中の『ゆめみたか』は今年1月に亡くなった田川律氏を追った2008年公開のドキュメンタリー。音楽評論家で晶文社が出した音楽本の翻訳者としても何度か目にした名前ですが、近年は“歌手”として様々なイベントに関わっていたようで、ひょんな出会いから追い続けることになった伊勢さんの撮った映像が、本人のひょうひょうとした個性と相俟(あいま)って何とも“ゆるやか”な作品に仕上がっています。1980年代に水牛楽団の高橋悠治氏らと共にその名をよく見かけましたが、昭和一ケタ(直後)世代の一人として戦後のサブカルチャー、特に音楽シーンに深く関わった豊富な経験の中には「替え歌」もありました。時代や社会を批評する精神から生まれた「替え歌」を諳んじる姿は、軍歌一色に染められた幼き時代へのアンチテーゼのようでもあり、寺の息子の音楽法話のようにも感じられました。何というか“自由”な雰囲気をまとった人というイメージです。
午後の『PascaLs』は、大編成のアコースティックバンド「パスカルズ」のライブ映像を中心とした構成。こちらは3年前に急逝したチェロの三木黃太氏が抜けて現在は13人。「パスカルズ」の名前だけはどこかで聞いた記憶がありましたが、あのイカ天キング「たま」の知久・石川両氏もメンバーです。そして、もう一人。大倉山駅近くにあった喫茶店「カフェ・グランデ」で生の演奏を聴いたことがあるチェロの坂本弘道氏も参加しています。鋸パフォーマンスも健在でしたが、僚友三木氏が抜けた後だけに、20年前の“はちゃめちゃさ”は薄れているように感じました。それは、チラシにもある「不在という在り方」という言葉通り、三木氏が演奏していたであろう場所の頭上に置かれた白い貝の輪と飛び立つ鳥のオブジェが、楽器を演奏している飛天につながるように見えたことと関係があるのかもしれません。ある人は彼らの音楽に多幸感を感じるそうです。天上の音楽ではありませんが、ライブはきっと映画の副題「しあわせのようなもの」みたいな不思議な空間なのでしょう。
忘れられる語り部 ― 2023年05月19日 19:28
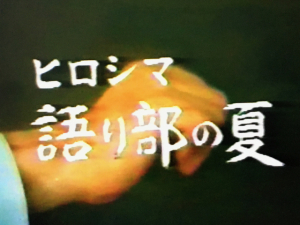
グローバルサウスの進展でもはや形骸化したとも言えるG7サミットが広島で開かれることで何かしらの意味を持つかのように伝えられていますが、少なくとも国際的な議論に参加できるような外交手腕を失って久しいこの国にかろうじて世界の関心が集まるものがあるとしたら、それはやはり“世界で最初の被爆地”というメッセージしかないのでしょう。
大陸に膨大な数の兵士を送り出した港がある軍都として知られた街は、大きな空襲の候補から外れ、たった一発の爆弾による被害効果を測るために選ばれました。その街で、被爆した同級生のほとんどを失った当時14歳の少年は、長ずるに地元の公務員として行政広報に携わり、最後は平和記念資料館の館長として知られるようになりました。
高橋昭博さん。原水爆禁止や被爆者運動に関わる傍ら、修学旅行で広島を訪ね、あるいは事前に平和学習を行う学校へ出向いては、生徒たちに自らの体験を語る個人的な活動を始めた最も初期の「語り部」の一人です。その経緯は、1978年に刊行された著書『ヒロシマ、ひとりからの出発』(ちくまブックス)に詳しく載っていますが、私が最初に知ったのは同年の8月15日に放映された『ヒロシマ語り部の夏』というドキュメンタリーです。
残念ながら、もうアーカイブスで観ることはできないようですが、著書同様に番組の中でも語っている言葉があります。それは、被爆時と同年齢の若者たちとの交流が自身の活動の出発点となったことに因縁を感じ、だからこそ彼らには「“戦争を体験しない”まま、若者としての平和で幸せな生活を送り続けてほしいと心から願わずにはおれない」と結んでいます。
番組を観た私はその年の暮れに広島を初めて訪ねました。小雪が降る中、市役所から出てきた高橋さんの面影は今でも良く覚えています。短い時間でしたが歓談し、翌日から向かったのは呉・江田島と岩国です。戦後33年を経て、すっかり変わった街の周りにある“変わらない風景と新たな戦前”を一体の現実として捉えたかったのでしょう。その認識は、バイデンが専用機で岩国基地へ降り立つ今、変わらないどころか深化しているとさえ思います。
大陸に膨大な数の兵士を送り出した港がある軍都として知られた街は、大きな空襲の候補から外れ、たった一発の爆弾による被害効果を測るために選ばれました。その街で、被爆した同級生のほとんどを失った当時14歳の少年は、長ずるに地元の公務員として行政広報に携わり、最後は平和記念資料館の館長として知られるようになりました。
高橋昭博さん。原水爆禁止や被爆者運動に関わる傍ら、修学旅行で広島を訪ね、あるいは事前に平和学習を行う学校へ出向いては、生徒たちに自らの体験を語る個人的な活動を始めた最も初期の「語り部」の一人です。その経緯は、1978年に刊行された著書『ヒロシマ、ひとりからの出発』(ちくまブックス)に詳しく載っていますが、私が最初に知ったのは同年の8月15日に放映された『ヒロシマ語り部の夏』というドキュメンタリーです。
残念ながら、もうアーカイブスで観ることはできないようですが、著書同様に番組の中でも語っている言葉があります。それは、被爆時と同年齢の若者たちとの交流が自身の活動の出発点となったことに因縁を感じ、だからこそ彼らには「“戦争を体験しない”まま、若者としての平和で幸せな生活を送り続けてほしいと心から願わずにはおれない」と結んでいます。
番組を観た私はその年の暮れに広島を初めて訪ねました。小雪が降る中、市役所から出てきた高橋さんの面影は今でも良く覚えています。短い時間でしたが歓談し、翌日から向かったのは呉・江田島と岩国です。戦後33年を経て、すっかり変わった街の周りにある“変わらない風景と新たな戦前”を一体の現実として捉えたかったのでしょう。その認識は、バイデンが専用機で岩国基地へ降り立つ今、変わらないどころか深化しているとさえ思います。
広報以下に堕したニュース記事 ― 2023年05月21日 19:31
地元の日本語教室で毎週作文を書いてもらっているベトナム人学習者が、先週、ニュースを題材に直近の社会状況についてコメントした文章を寄せてきました。彼女の作文は、そのニュースで取り上げられた対策が母国で起きた事件を防ぐために有効ではないかと考えたものですが、届いたメールに記事のURLも載っていたので、リンクを追ってみて辿り着いたのがこの記事です。ベトナムは近年モバイル決済が急速に拡がっているようで、若年層人口が多いことからITサービスへの関心も大きく、そうした業界で働く本人も新しいサービスに興味をそそられた様子でした。
作文については一通り日本語らしい表現への添削を施して、いつものように“例”の一つとして示しましたが、元になった記事を読んでいてひっかかるところがいくつもありました。
まず、「子供の行方不明」というタイトルと夜道を歩くような黒地のイラストが不安を煽っているように見えます。冒頭の「年間1000人以上。」という体言止めの一文もそれに拍車をかけています。警察に行方不明として届けられた子供(9歳以下)の人数ですが、直後の小見出しに毎年1000人以上と強調されています。そこで掲載された図を見ると、2017(平成29)年からの5年間はほぼ横ばいです。その後コロナ禍の影響がどのように出たかは示されていませんので、この期間に限っての状況と理解するしかありませんが、元ネタが警察庁とあるのでWebで検索したところ、昨年6月に警察庁・少年課が発表した資料に行き当たりました。
それによれば、行方不明者の全体数は2012年から大きな変化は無く、毎年8万人前後が続いています。ただし、その多くは10〜20代の若者と80歳以上の老人に集中しています。ちなみに原因・動機別では疾病や家庭・職業関係が6割弱を占めていました。また、資料の最後にまとめられた年次別の1956年以降の受理状況数で見ると、成人・少年(0〜19歳)別の記録が残っている1966年以降、次のような傾向があることがわかりました。2021年までの55年間の統計で、総数は1981年と2002年前後の二つのピークはあるものの、長期に渡って漸減傾向にあり、それは変わっていません。概数では最初の10年平均が93000人、直近10年が83000人と10000人減っています。また、直近2年は8万人を切っています。同時期の少年の割合は0.44から0.21へ、逆に全体の所在確認率は0.74から0.98と上がっています。つまり子供を含む少年の行方不明は減っており、行方不明後の所在確認も多くなってきたということです。
もちろん、家族が心配することそのものは、個々の事情があっても大きく変わることはないでしょう。ただ、実態をまとめた報告書を読む限りでは、この5年の傾向だけではつかめないものの、行方不明は減っていることになります。それが、何故このような不安を煽る表現になるのでしょうか。
それは、記事の次項目以下を読めばわかります。ごく一部の自治体が行っているマイナンバーカードを子供に持たせ、その公的個人認証(ICチップ)を登下校の管理に使おうという施策の導入を紹介するためです。他にも長時間バッテリーの小型端末による「見守り人アプリ」(あの、COCOAを連想させます)の紹介があって、ご丁寧にサービスを行っている民間会社の固有名詞と社長名まで載せてあります。
また、記事の内容そのものとは別に、次のような言い回しが多数あります。「といいます」「そうですが…」、「としています」「ということです」。裏取りをするようなケースではありませんが、記者自らが調査・確認しようとする姿勢が全く感じられません。大阪府警の「5つの約束」にいたっては府の広報そのものです。
以上、ミスリードと言えるかは微妙なところですが、このニュースに限らず、記事の品質は目に見えて落ち続けています。昨年、留学生と一緒に読んだ“日経”でも日本語としておかしな表現にいくつも出会いました。ChatGPTに置き換わるのも時間の問題のような気がしています。
ちなみに学習者の二人には、メディアリテラシーの基本的な考え方として、自分自身で調べられない場合は、できるだけ複数のソースを比べながら地道に信頼できるメディアを探す必要がある時代になっていることを伝えました。私の場合は、東京新聞と「TBS報道特集」、10数人のTwitterフォローと外国通信社の日本記事を頼りにしています。^^;
作文については一通り日本語らしい表現への添削を施して、いつものように“例”の一つとして示しましたが、元になった記事を読んでいてひっかかるところがいくつもありました。
まず、「子供の行方不明」というタイトルと夜道を歩くような黒地のイラストが不安を煽っているように見えます。冒頭の「年間1000人以上。」という体言止めの一文もそれに拍車をかけています。警察に行方不明として届けられた子供(9歳以下)の人数ですが、直後の小見出しに毎年1000人以上と強調されています。そこで掲載された図を見ると、2017(平成29)年からの5年間はほぼ横ばいです。その後コロナ禍の影響がどのように出たかは示されていませんので、この期間に限っての状況と理解するしかありませんが、元ネタが警察庁とあるのでWebで検索したところ、昨年6月に警察庁・少年課が発表した資料に行き当たりました。
それによれば、行方不明者の全体数は2012年から大きな変化は無く、毎年8万人前後が続いています。ただし、その多くは10〜20代の若者と80歳以上の老人に集中しています。ちなみに原因・動機別では疾病や家庭・職業関係が6割弱を占めていました。また、資料の最後にまとめられた年次別の1956年以降の受理状況数で見ると、成人・少年(0〜19歳)別の記録が残っている1966年以降、次のような傾向があることがわかりました。2021年までの55年間の統計で、総数は1981年と2002年前後の二つのピークはあるものの、長期に渡って漸減傾向にあり、それは変わっていません。概数では最初の10年平均が93000人、直近10年が83000人と10000人減っています。また、直近2年は8万人を切っています。同時期の少年の割合は0.44から0.21へ、逆に全体の所在確認率は0.74から0.98と上がっています。つまり子供を含む少年の行方不明は減っており、行方不明後の所在確認も多くなってきたということです。
もちろん、家族が心配することそのものは、個々の事情があっても大きく変わることはないでしょう。ただ、実態をまとめた報告書を読む限りでは、この5年の傾向だけではつかめないものの、行方不明は減っていることになります。それが、何故このような不安を煽る表現になるのでしょうか。
それは、記事の次項目以下を読めばわかります。ごく一部の自治体が行っているマイナンバーカードを子供に持たせ、その公的個人認証(ICチップ)を登下校の管理に使おうという施策の導入を紹介するためです。他にも長時間バッテリーの小型端末による「見守り人アプリ」(あの、COCOAを連想させます)の紹介があって、ご丁寧にサービスを行っている民間会社の固有名詞と社長名まで載せてあります。
また、記事の内容そのものとは別に、次のような言い回しが多数あります。「といいます」「そうですが…」、「としています」「ということです」。裏取りをするようなケースではありませんが、記者自らが調査・確認しようとする姿勢が全く感じられません。大阪府警の「5つの約束」にいたっては府の広報そのものです。
以上、ミスリードと言えるかは微妙なところですが、このニュースに限らず、記事の品質は目に見えて落ち続けています。昨年、留学生と一緒に読んだ“日経”でも日本語としておかしな表現にいくつも出会いました。ChatGPTに置き換わるのも時間の問題のような気がしています。
ちなみに学習者の二人には、メディアリテラシーの基本的な考え方として、自分自身で調べられない場合は、できるだけ複数のソースを比べながら地道に信頼できるメディアを探す必要がある時代になっていることを伝えました。私の場合は、東京新聞と「TBS報道特集」、10数人のTwitterフォローと外国通信社の日本記事を頼りにしています。^^;