危機感が伝わらない政策 ― 2020年04月12日 10:45
ここ数日、以前から集中的に録り始めたテレビ番組を観ている。毎週土曜日の夜に放送されている「NHKスペシャル 新型コロナウィルス:瀬戸際の攻防」である。3月末頃からここ数日の社会の動きと併せていろいろと考えることが多かったので、自分の言葉でまとめてみた。
番組は、厚労省の一室で新型コロナウィルス感染拡大の阻止を検討している感染症対策チームの専門家を現場を含めて直接取材しているものだ。首相会見を始めとする公式な“取材”だけでは到底わからない事情がよくまとめられている。その責任の重大さを認識している専門家の言葉の端々から苦渋が聞こえる。2月末の局所(クラスター)感染状況からその後の孤発感染者(いわゆる局所でない感染ルートが判明しない患者)の拡がりに対策チームが頭を抱えている。感染ルートの把握が事実上困難になったからには積極的に大規模な接触防止を図らなければならない。“緊急事態宣言”が必要となる。だが、その先は「政策」であって彼ら自身がイニシアティブを取るものにはならない。たとえ、それが“補償無き自粛”の要請であっても、感染以前に生きる術が断たれる可能性を持つものだったとしても…。
彼らは日本の医療の現状を良く知っている。この7年間、医療を含む社会システムが極端に脆弱化していることも。そのような条件下での最適解を考えなければならない事態に置かれ、強い焦燥感に駆られている。だから、司会者の“まとめ”ではなく、彼らの発する“言葉”に含まれる危機感を共有しなければならないと感じた。感染の終息は長引く可能性が高く、いまだ光明は見えていない。しかし、いたずらに悲観しても何も生み出さない。愚策を続ける現政権下でどのように科学的な根拠ある情報を選択摂取して自らの行動につなげるかが問われている。
番組は、厚労省の一室で新型コロナウィルス感染拡大の阻止を検討している感染症対策チームの専門家を現場を含めて直接取材しているものだ。首相会見を始めとする公式な“取材”だけでは到底わからない事情がよくまとめられている。その責任の重大さを認識している専門家の言葉の端々から苦渋が聞こえる。2月末の局所(クラスター)感染状況からその後の孤発感染者(いわゆる局所でない感染ルートが判明しない患者)の拡がりに対策チームが頭を抱えている。感染ルートの把握が事実上困難になったからには積極的に大規模な接触防止を図らなければならない。“緊急事態宣言”が必要となる。だが、その先は「政策」であって彼ら自身がイニシアティブを取るものにはならない。たとえ、それが“補償無き自粛”の要請であっても、感染以前に生きる術が断たれる可能性を持つものだったとしても…。
彼らは日本の医療の現状を良く知っている。この7年間、医療を含む社会システムが極端に脆弱化していることも。そのような条件下での最適解を考えなければならない事態に置かれ、強い焦燥感に駆られている。だから、司会者の“まとめ”ではなく、彼らの発する“言葉”に含まれる危機感を共有しなければならないと感じた。感染の終息は長引く可能性が高く、いまだ光明は見えていない。しかし、いたずらに悲観しても何も生み出さない。愚策を続ける現政権下でどのように科学的な根拠ある情報を選択摂取して自らの行動につなげるかが問われている。
脆弱化した社会 ― 2020年04月18日 10:47
政府が一律10万円を配るという。住所不定のホームレスなど仮に身分を証明できない人には渡らない可能性もある。それでもコロナ“禍”でいきなり収入を断たれた人にとっては喫緊の問題解決につながるかもしれない。それがすぐにでも届くならば…。そして一息ついたらすぐにでも次の手を考えるべきだろう。収入が減らなかったり余裕のある人は、厳しい状況にいる人々を助けるための基金やクラウドファンディングに転用すればいい。政府がそれを“信頼できる”第三者に委ねられるのなら、それはそれでかまわない。“信頼”できるところへ有効に使いたい。
問題点を挙げればキリがないが、現状で最大の懸案は社会システムそのものが崩壊しないようにするために何をするかだと思う。繁雑でな無駄な事務手続きを減らし、当面の間、社会生活に最低限必要なことに力を注ぐ工夫が大事だ。セーフティーネットの再構築は社会全体を護る意味でも今後ますます重要になるが、直近は正規・非正規に関わらず、現時点で自粛要請の対象に入らない日常生活を支える職場を中心に、“公的”な仕事を最前線で担っている人を護ることだ。
また、医療の現状が重症度に応じて優先的に選別する「トリアージ」の“前段階”にあるとしても、感染防止のためのマスクや消毒液の増産・輸入・頒布を本気で検討して欲しい(自国でできないなら隣国に頼ろう)。ネットでの高額販売や私益のための配布など間接的に広く頒布されるべきものを妨害する行為を厳しく罰した上で、感染の可能性の高いところから順次に行き渡る実用的な供給対策を考えてもらいたい。
それにしても、ここまで社会の脆弱化が進んでいたことに驚く。政府を始め、主要な自治体の長の言葉もその多くが信頼に足るものではなくなっていたが、“効率”や“経済合理性”に偏って、暮らしを持続させる上での基本的なインフラについて縮減・廃止を行ってきたツケがこのコロナ“禍”において大きく響いている。膨大な予算を使って“防衛”兵器を購入しながら、水道民営化や種子法廃止など社会システムを支える仕組みへの破壊が今なお、この時点でも進んでいることにおののく。
日本人が真剣に後の世代のことを考えているとは到底思えない。後の世代は、私たち日本人が“嘘つき”で無能無策な為政者を選んできたことに怨嗟の声をきっと挙げるだろう。いや、“選びさえしなかった”ことに…。それは率直に謝るしかないのだが、コロナ後の社会をどうやって生きるのか、“先”を進んでいる東アジアの隣人達にも教えを請う必要がある。彼らに学ぶべきことは多い。
問題点を挙げればキリがないが、現状で最大の懸案は社会システムそのものが崩壊しないようにするために何をするかだと思う。繁雑でな無駄な事務手続きを減らし、当面の間、社会生活に最低限必要なことに力を注ぐ工夫が大事だ。セーフティーネットの再構築は社会全体を護る意味でも今後ますます重要になるが、直近は正規・非正規に関わらず、現時点で自粛要請の対象に入らない日常生活を支える職場を中心に、“公的”な仕事を最前線で担っている人を護ることだ。
また、医療の現状が重症度に応じて優先的に選別する「トリアージ」の“前段階”にあるとしても、感染防止のためのマスクや消毒液の増産・輸入・頒布を本気で検討して欲しい(自国でできないなら隣国に頼ろう)。ネットでの高額販売や私益のための配布など間接的に広く頒布されるべきものを妨害する行為を厳しく罰した上で、感染の可能性の高いところから順次に行き渡る実用的な供給対策を考えてもらいたい。
それにしても、ここまで社会の脆弱化が進んでいたことに驚く。政府を始め、主要な自治体の長の言葉もその多くが信頼に足るものではなくなっていたが、“効率”や“経済合理性”に偏って、暮らしを持続させる上での基本的なインフラについて縮減・廃止を行ってきたツケがこのコロナ“禍”において大きく響いている。膨大な予算を使って“防衛”兵器を購入しながら、水道民営化や種子法廃止など社会システムを支える仕組みへの破壊が今なお、この時点でも進んでいることにおののく。
日本人が真剣に後の世代のことを考えているとは到底思えない。後の世代は、私たち日本人が“嘘つき”で無能無策な為政者を選んできたことに怨嗟の声をきっと挙げるだろう。いや、“選びさえしなかった”ことに…。それは率直に謝るしかないのだが、コロナ後の社会をどうやって生きるのか、“先”を進んでいる東アジアの隣人達にも教えを請う必要がある。彼らに学ぶべきことは多い。
苛政と傷寒に起ち上がった人々 ― 2020年04月18日 10:51
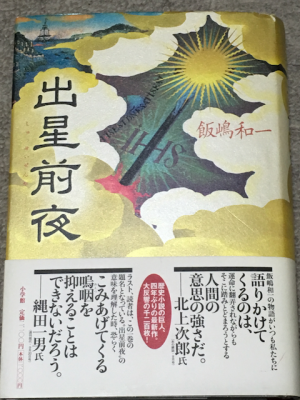
いわゆる漢方と呼ばれる東アジアの伝統医学の中に『傷寒論』というものがある。後漢時代の医師張仲景によって編集された。「傷寒」とは急性熱性疾患を広く言い表す言葉だ。この傷寒の流行を一つのきっかけに起きた大規模な住民蜂起を背景とする歴史小説がある。飯嶋和一の『出星前夜』。江戸時代初期の「島原の乱」を舞台に、転封でやってきた大名松倉家の苛政に苦しむ元キリシタン達が時代に翻弄されるように蜂起へと起ち上がった事情と結末を描いている。主人公は「天草四郎」ではなく、島原半島南部、南目(みなみめ)の有家(ありえ)に住む篤農家甚右衛門(後の蜂起勢参謀鬼塚監物)と若衆の一人矢矩鍬之介(後の医師北山寿安)。
作家は、デビュー三作目の『始祖鳥記』以来、あまり陽は当たらないけれど特異な人物や、歴史的事件の背景に連なる“個人”のありようを題材に、数少ない長編小説を書き下ろしてきたが、この作品も前作から4年後に出ている。時に饒舌とも思われるような繰り返しの描写が、登場人物の“人間”としての造形を読む者に浸透させる。だから、単行本で500頁を超える大作にもなるが、いつも読後は充足感で一杯だ。
苛政に苦しめられていた人々に“傷寒”というさらなる災禍が訪れる。蜂起が引き金とはいえ、その“信仰”により誅殺された人々と、“いのち”を救う医師の物語は今を考えさせられる。
作家は、デビュー三作目の『始祖鳥記』以来、あまり陽は当たらないけれど特異な人物や、歴史的事件の背景に連なる“個人”のありようを題材に、数少ない長編小説を書き下ろしてきたが、この作品も前作から4年後に出ている。時に饒舌とも思われるような繰り返しの描写が、登場人物の“人間”としての造形を読む者に浸透させる。だから、単行本で500頁を超える大作にもなるが、いつも読後は充足感で一杯だ。
苛政に苦しめられていた人々に“傷寒”というさらなる災禍が訪れる。蜂起が引き金とはいえ、その“信仰”により誅殺された人々と、“いのち”を救う医師の物語は今を考えさせられる。
追悼 佐々部清監督 ― 2020年04月20日 10:52

先週末に亡くなった大林宣彦監督の追悼番組や映画が次々に放映されているようだ。代表作『時をかける少女』が有名だが、『転校生』・『異人たちとの夏』・『青春デンデケデケデケ』など印象に残る数々の作品を世に出した日本を代表する監督であることは間違いないから、その功績に見合った回顧がこれからもしばらくは続くだろう。
一方で、先月末に62歳の若さで亡くなった映画監督佐々部清の話題があまりに少ないような気がするのは“僻(ひが)め”というものだろうか。横山秀夫原作の『半落ち』や、こうの史代原作の『夕凪の街 桜の国』など、それなりに話題になった作品も手掛けているのだが、いずれも“大作”と言うよりは“佳品”という言葉が相応しいものだけに、職人的な作風が却って多くの人の記憶に残らないのだろうか。もとより、私の情報摂取量は一般より極端に少ないこともあって、単に知らないだけなのかもしれないが、これらの“佳品”を作り続けた監督の急逝が広く悼まれることがなかったら、それはとても寂しい。
私が佐々部清の名前を意識するようになったのは『半落ち』ではない。同じ年に公開された『チルソクの夏』という、それこそ“佳品”に相応しい映画だった。監督の出身地である下関には隣国釜山との定期航路があり、両市の様々な文化交流の一つとして相互に隔年開催する合同の陸上競技大会があった。その代表選手として大会に出場した日韓高校生の初恋の物語である。戒厳令下の釜山で宿舎から抜け出し、ロミオとジュリエット張りの逢瀬で来年の七夕(チルソク:칠석)に再会を約す。若さを象徴するような4人の女優による陸上競技の撮影が行われると共に、70年代後半の時代を髣髴とさせる背景も描かれた。当時『ジョゼと虎と魚たち』で注目を浴び始めた上野樹里が主人公の親友役で出ている。
離れたままに思いを伝えるため、互いに隣国の言葉で手紙を交わすことになるのだが、最後は25年ぶりの再会へとハングルで書かれた呼び出しのメモが届く。お互い違う道を歩んだからと言って、心を通わした言葉は残る。そういえば、佐々部清はあの『フォロー・ミー』が好きだったという。コミュニケーションを取り戻そうとする行動はあの映画にも貫かれていた。
一方で、先月末に62歳の若さで亡くなった映画監督佐々部清の話題があまりに少ないような気がするのは“僻(ひが)め”というものだろうか。横山秀夫原作の『半落ち』や、こうの史代原作の『夕凪の街 桜の国』など、それなりに話題になった作品も手掛けているのだが、いずれも“大作”と言うよりは“佳品”という言葉が相応しいものだけに、職人的な作風が却って多くの人の記憶に残らないのだろうか。もとより、私の情報摂取量は一般より極端に少ないこともあって、単に知らないだけなのかもしれないが、これらの“佳品”を作り続けた監督の急逝が広く悼まれることがなかったら、それはとても寂しい。
私が佐々部清の名前を意識するようになったのは『半落ち』ではない。同じ年に公開された『チルソクの夏』という、それこそ“佳品”に相応しい映画だった。監督の出身地である下関には隣国釜山との定期航路があり、両市の様々な文化交流の一つとして相互に隔年開催する合同の陸上競技大会があった。その代表選手として大会に出場した日韓高校生の初恋の物語である。戒厳令下の釜山で宿舎から抜け出し、ロミオとジュリエット張りの逢瀬で来年の七夕(チルソク:칠석)に再会を約す。若さを象徴するような4人の女優による陸上競技の撮影が行われると共に、70年代後半の時代を髣髴とさせる背景も描かれた。当時『ジョゼと虎と魚たち』で注目を浴び始めた上野樹里が主人公の親友役で出ている。
離れたままに思いを伝えるため、互いに隣国の言葉で手紙を交わすことになるのだが、最後は25年ぶりの再会へとハングルで書かれた呼び出しのメモが届く。お互い違う道を歩んだからと言って、心を通わした言葉は残る。そういえば、佐々部清はあの『フォロー・ミー』が好きだったという。コミュニケーションを取り戻そうとする行動はあの映画にも貫かれていた。
これからの原尞は? ― 2020年04月23日 10:54
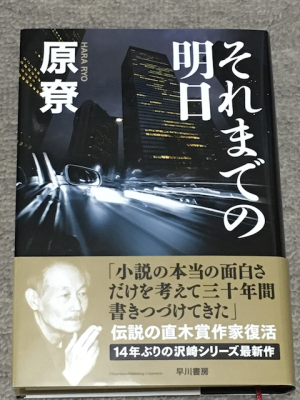
昔から“本格推理”と形容される作品にはあまり興味が湧かない。同様に“○○節”と呼ばれる叙情に傾く文体も苦手で、そういう傾向が強い推理・冒険小説を敬遠してきた。だから、どちらかと言えば“乾いた”文体を多く好んで読んで来たような気がする。寡作の作家原尞の作品もその一つだ。その最新作が一昨年に刊行された『それまでの明日』である。
探偵「沢崎」が主人公の連作とはいえ、14年ぶりともなると本作で初めて知ったという若い読者もいるだろう。警察や“暴力団”が出てくるが、いわゆる“ノワール”とは違うし、興信所が活躍するミステリーとも違う。やはり、著者が心酔するレイモンド・チャンドラーに代表されるハードボイルドに近いが、探偵事務所のある新宿が舞台の中心であることから、細かく描かれた背景に臨場感がある。私のような、酒をほとんど飲まず、煙草は二十歳前に試しただけの田舎者をして、そう強く感じさせるだけの丁寧な描写が真骨頂だ。
50代となった探偵の、依頼人や様々な関係者とのつながりは、今までより少し緩やかになった“きらい”はあるが、それは主人公以外に携帯電話を持たない人物が出てこなくなった時代を一面で表しているのかもしれない。“それまで”あった社会が急速に変わってしまった後、探偵として主人公沢崎がどのように処していくのかが次作では描かれるのかもしれないが、果たしてそれはいつ頃のことになるだろうか。
探偵「沢崎」が主人公の連作とはいえ、14年ぶりともなると本作で初めて知ったという若い読者もいるだろう。警察や“暴力団”が出てくるが、いわゆる“ノワール”とは違うし、興信所が活躍するミステリーとも違う。やはり、著者が心酔するレイモンド・チャンドラーに代表されるハードボイルドに近いが、探偵事務所のある新宿が舞台の中心であることから、細かく描かれた背景に臨場感がある。私のような、酒をほとんど飲まず、煙草は二十歳前に試しただけの田舎者をして、そう強く感じさせるだけの丁寧な描写が真骨頂だ。
50代となった探偵の、依頼人や様々な関係者とのつながりは、今までより少し緩やかになった“きらい”はあるが、それは主人公以外に携帯電話を持たない人物が出てこなくなった時代を一面で表しているのかもしれない。“それまで”あった社会が急速に変わってしまった後、探偵として主人公沢崎がどのように処していくのかが次作では描かれるのかもしれないが、果たしてそれはいつ頃のことになるだろうか。