個人的な物語が生み出すもの ― 2020年04月28日 10:56
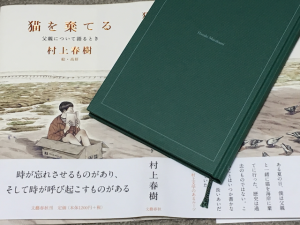
昨年「文藝春秋」に掲載された村上春樹の回想記が『猫を棄てる』という書名で単行本化された。後に絶縁状態となる父親との平凡な風景の記憶を手がかりにして、父から“受け取り、引き継いだ”ものを淡々と書き上げた短い文章である。戦後、小さな菩薩の入ったガラスケースを前に毎朝お経を唱えていたという父親が、小学校低学年だった著者に伝えた“残忍”な心性というものを核として、村上春樹の小説を貫く歴史意識が語られている。それはある意味、作家ならではの独白に近いが、父親と息子という関係であれば、伝えられる内容は様々に違えど、誰しもが似たような経験を持った可能性はあるかもしれない。ただ、それを思い起こすことができるかどうかは別の問題だ。
私は18歳で就職してから両親と離れる一人暮らしを何度も繰り返した。明治生まれの父親とは、考えられる限りにおいて違うことを指向し、およそ会話らしきものがないままに、父が癌で亡くなるまでの八年を過ごした。小さい頃から何かを教えてもらったということがない。二人でキャッチボールをした記憶がわずかにあるぐらいだ。平日休みの仕事なので、父は“一人で”パチンコに行くか、写真を撮るか、油絵を描いていた。戦時中は木更津の高射砲陣地に配属されると内務班で新兵イジメを受け、そのどちらか、あるいは両方のせいで難聴となり、復員後は補聴器を付けるようになった。父の軍隊経験の話からは日本人の“狭量”しか感じるものはなかった。いつのまにか、私もそれを“受け取り、引き継いで”いたようで、繰り返し先輩や上司とぶつかりながら一人でできる仕事を探し続けてきた。そんなことも「個人的な物語であると同時に、僕らの暮らす世界全体を作り上げている大きな物語の一部でもある。ごく微少な一部だが、それでもひとつのかけらであるという事実に間違いはない」と言えるだろうか。
単行本の装画と挿絵は高妍という年若い台湾のイラストレーターの作品である。村上春樹は本のあとがきで「彼女の絵にはどこかしら、不思議と懐かしさのようなものが感じられる」と書いた。その通りだと思う。
私は18歳で就職してから両親と離れる一人暮らしを何度も繰り返した。明治生まれの父親とは、考えられる限りにおいて違うことを指向し、およそ会話らしきものがないままに、父が癌で亡くなるまでの八年を過ごした。小さい頃から何かを教えてもらったということがない。二人でキャッチボールをした記憶がわずかにあるぐらいだ。平日休みの仕事なので、父は“一人で”パチンコに行くか、写真を撮るか、油絵を描いていた。戦時中は木更津の高射砲陣地に配属されると内務班で新兵イジメを受け、そのどちらか、あるいは両方のせいで難聴となり、復員後は補聴器を付けるようになった。父の軍隊経験の話からは日本人の“狭量”しか感じるものはなかった。いつのまにか、私もそれを“受け取り、引き継いで”いたようで、繰り返し先輩や上司とぶつかりながら一人でできる仕事を探し続けてきた。そんなことも「個人的な物語であると同時に、僕らの暮らす世界全体を作り上げている大きな物語の一部でもある。ごく微少な一部だが、それでもひとつのかけらであるという事実に間違いはない」と言えるだろうか。
単行本の装画と挿絵は高妍という年若い台湾のイラストレーターの作品である。村上春樹は本のあとがきで「彼女の絵にはどこかしら、不思議と懐かしさのようなものが感じられる」と書いた。その通りだと思う。
言語交換ソングズ ― 2020年04月29日 10:58
日曜日の夜、TOKYO FMで放送された村上RADIOの13回目を聴いた。“言語交換ソングズ”と題して歌詞の言語を変えて唄った音楽がいろいろと並べられている。日本の歌手が外国語の歌を、外国の歌手が日本語の歌を、母語に変えたり変えなかったり。中には動物の鳴き声で構成された有名な楽曲もある。
「The Covers」のような日本人同士の歌ではなく、言葉の違いを超えて音を楽しむことの面白さと、そこに横たわる普遍性のようなものが感じられて、良かった。冒頭、サザン・オールスターズの『忘れられたBig Wave』が流れたときは驚いたが、山下達郎の『踊ろよ、フィッシュ』と併せて英語にそのまま乗るところは、ポップスの王道ならではか。真心ブラザースが唄うボブ・ディランの「My Back Pages」は何も知らずに聴いていたら吉田拓郎の歌に聞こえる。それだけ、あの時代には大きな影響があったということだろう。坂本九の『明日があるさ』のレゲエ版や、フォスター『金髪のジェニー』の沖縄版には南の風が吹いている。
Radicoのタイムフリーは終了してしまったが、Youtubeでも出ているようなので、関心があればどうぞ…。
「The Covers」のような日本人同士の歌ではなく、言葉の違いを超えて音を楽しむことの面白さと、そこに横たわる普遍性のようなものが感じられて、良かった。冒頭、サザン・オールスターズの『忘れられたBig Wave』が流れたときは驚いたが、山下達郎の『踊ろよ、フィッシュ』と併せて英語にそのまま乗るところは、ポップスの王道ならではか。真心ブラザースが唄うボブ・ディランの「My Back Pages」は何も知らずに聴いていたら吉田拓郎の歌に聞こえる。それだけ、あの時代には大きな影響があったということだろう。坂本九の『明日があるさ』のレゲエ版や、フォスター『金髪のジェニー』の沖縄版には南の風が吹いている。
Radicoのタイムフリーは終了してしまったが、Youtubeでも出ているようなので、関心があればどうぞ…。
ヤジを守るメディア ― 2020年04月30日 11:01
今年2月に放送されギャラクシー賞月間賞を受けたHBCのドキュメンタリー『ヤジと民主主義 ~警察が排除するもの~』の拡大版(46分)が制作され、先日(日曜深夜)放映された。その内容がYoutubeのHBC公式チャンネルで公開されている。
昨年7月の参議院選挙において、札幌での安倍首相の応援演説中、ヤジを飛ばした男性や、反対の声を挙げた女子学生、プラカードを持っていた女性などが次々と警察によって排除された。現場を始め、問題が提議された道議会でも警察は法的根拠を明示できず、排除された人が提訴した地裁においても蓋然性の低い“言い訳”に終始している。同様の事例が他にない限り、政治的な中立性を保っているとはとても言えない。「走狗」という言葉が頭をよぎる。現場で撮影された多くの映像がそれを雄弁に示している。
「誰かの権利が奪われることに無関心な社会は権力の暴走を許すことにつながる」というナレーションの後、番組は元道警幹部の言葉を次のように接いだ。
「今回の場合、怖ろしいと思うのは、これをたくさんのマスコミのカメラのいる前で堂々とやったということです。あなたたち無視されたんです。法的な根拠のないことが平気で行われているんです、あちこちで。皆さんが知らないだけで。国民の権利がわからないところで、何て言うんですか。危険にさらされている部分があるんだよということを、皆さん方わかっていないんじゃないでしょうかね。」
そして、「あの日、警察に排除された人達に対し、救いの手を差し伸べる人はいませんでした」と述べ、取材した当事者三人それぞれの言葉を流した。
「いや、ほんとに助けて欲しくて。何かずっと怖かったんですよ。なんで見ているだけ、撮っているだけなのっていう感じで。すごい悲しかったですね」
「日本社会の中で、その他とは違うものを冷遇するとかっていう風潮はやっぱり強まっているのかもしれませんけどね」
「私、そんなに先が無いと思うので、皆にもひとりでも気づいて行って欲しい。それが願いですよね」
番組の最後はこう締めくくられた「ヤジすらも言えない社会になるのか。小さな自由が排除されたその先に待つものとは」。法律を守らない為政者を、法律では守れないという現実がそれを示している。
昨年7月の参議院選挙において、札幌での安倍首相の応援演説中、ヤジを飛ばした男性や、反対の声を挙げた女子学生、プラカードを持っていた女性などが次々と警察によって排除された。現場を始め、問題が提議された道議会でも警察は法的根拠を明示できず、排除された人が提訴した地裁においても蓋然性の低い“言い訳”に終始している。同様の事例が他にない限り、政治的な中立性を保っているとはとても言えない。「走狗」という言葉が頭をよぎる。現場で撮影された多くの映像がそれを雄弁に示している。
「誰かの権利が奪われることに無関心な社会は権力の暴走を許すことにつながる」というナレーションの後、番組は元道警幹部の言葉を次のように接いだ。
「今回の場合、怖ろしいと思うのは、これをたくさんのマスコミのカメラのいる前で堂々とやったということです。あなたたち無視されたんです。法的な根拠のないことが平気で行われているんです、あちこちで。皆さんが知らないだけで。国民の権利がわからないところで、何て言うんですか。危険にさらされている部分があるんだよということを、皆さん方わかっていないんじゃないでしょうかね。」
そして、「あの日、警察に排除された人達に対し、救いの手を差し伸べる人はいませんでした」と述べ、取材した当事者三人それぞれの言葉を流した。
「いや、ほんとに助けて欲しくて。何かずっと怖かったんですよ。なんで見ているだけ、撮っているだけなのっていう感じで。すごい悲しかったですね」
「日本社会の中で、その他とは違うものを冷遇するとかっていう風潮はやっぱり強まっているのかもしれませんけどね」
「私、そんなに先が無いと思うので、皆にもひとりでも気づいて行って欲しい。それが願いですよね」
番組の最後はこう締めくくられた「ヤジすらも言えない社会になるのか。小さな自由が排除されたその先に待つものとは」。法律を守らない為政者を、法律では守れないという現実がそれを示している。