諷喩としての狂言 ― 2024年06月03日 15:23

駅周辺の高層ビル拡張工事は依然としてカオス状態にあると、渋谷を訪ねる度に再確認させられます。今日は「セルリアンタワー」能楽堂に「狂言やるまい会」を観に行ったのですが、東横線の地下駅から「スクランブルスクエア」を横切り、JRの西口改札前を抜けて、玉川通りを渡る歩道橋に登った頃、ようやく人心地がついたと思ったら、正面に「サクラステージ」なる商業施設が現れました。「一風堂」(ラーメン店ではない)や「ロゴスキー」があった頃の桜丘がもうすっかり一変しているのには驚きます。
さて、番組は『音曲聟』・『瓜盗人』・『連尺』という狂言三番。和泉流狂言方野村又三郎家に連なる面々による公演です。いずれもあまり見かけない演目で、音曲や、笛に合わせた舞、男女の商売人による掛け合いなど、演者それぞれに挑戦する姿勢が感じられるプログラムになっています。
『音曲聟』は奧津健一郎さんが聟、健太郎さんが舅役。実の親子が舞台では義理の関係になります。大柄で衣装映えする健一郎さんだけに、聟入りの挨拶の教えを請う“何某”に出で立ちを褒められて喜ぶところなど、“愚かさ”の表現も巧みです。“音曲”は節を付けて話す、いわばミュージカルのようなものですが、そんな挨拶を受けて思わず噴きだす舅と太郎冠者ですが、これが“当世風”なのかと合わせるところは人が良い。酒が入って鷹揚になるとしまいには双之舞まで披露します。なにか能のカリカチュアにもなっているような不思議な演目です。
『瓜盗人』は『盆山』のように垣根を壊す所作が入る盗人の話。畑主がカカシに使うのが翁面で、瓜を盗られた後に自ら付けてカカシに化けます。舞台で付けるところは「翁」を連想させますし、盗人が祇園会の出し物になぞらえてカカシ(実は畑主)と遣り取りする場面では唄(今様?)や囃子方の笛が入るなど、こちらも能の雰囲気が漂います。一方で月明かりの深夜という時間設定が、寝転びながら瓜を探す狂言らしい所作には良く合っています。
『連尺』は背負子の紐。Webで検索するとその意味は出ますが、語源がわからりません。“尺”が30cm前後の長さの単位であるとしたら、背負子紐が身体に密着する肩当ての太い部分がそれにあたります。正面から見て並んだその姿が連なっているところから付けた名前なのでしょうか。演目の内容は、新しい市(いち)が立つことを聞いた商売人が、永代の権利欲しさで一番最初に店を出そうと争う話です。女の歌賃(餅のこと。搗ち飯)売りと男の絹布売りが、口喧嘩から歌合戦、足押(すねを押し合う足相撲)、さらには相撲で決着を付けるという騒ぎになります。ところどころにセクハラめいた所作もある中、いずれも男が負けを認めないのは現代に通じます。明治以降、公序良俗に反するとして上演禁止になっていたものを当代又三郎師が復曲したそうです。
狂言は諷刺の芸。『光る君へ』でも、散楽が演じられたり、『白氏文集・新楽府』の諷諭が語られましたが、時代(とき)の権威に抗う姿勢は、豊穣な“対向文化”を育ててきたことの一つの象徴でもあります。
さて、番組は『音曲聟』・『瓜盗人』・『連尺』という狂言三番。和泉流狂言方野村又三郎家に連なる面々による公演です。いずれもあまり見かけない演目で、音曲や、笛に合わせた舞、男女の商売人による掛け合いなど、演者それぞれに挑戦する姿勢が感じられるプログラムになっています。
『音曲聟』は奧津健一郎さんが聟、健太郎さんが舅役。実の親子が舞台では義理の関係になります。大柄で衣装映えする健一郎さんだけに、聟入りの挨拶の教えを請う“何某”に出で立ちを褒められて喜ぶところなど、“愚かさ”の表現も巧みです。“音曲”は節を付けて話す、いわばミュージカルのようなものですが、そんな挨拶を受けて思わず噴きだす舅と太郎冠者ですが、これが“当世風”なのかと合わせるところは人が良い。酒が入って鷹揚になるとしまいには双之舞まで披露します。なにか能のカリカチュアにもなっているような不思議な演目です。
『瓜盗人』は『盆山』のように垣根を壊す所作が入る盗人の話。畑主がカカシに使うのが翁面で、瓜を盗られた後に自ら付けてカカシに化けます。舞台で付けるところは「翁」を連想させますし、盗人が祇園会の出し物になぞらえてカカシ(実は畑主)と遣り取りする場面では唄(今様?)や囃子方の笛が入るなど、こちらも能の雰囲気が漂います。一方で月明かりの深夜という時間設定が、寝転びながら瓜を探す狂言らしい所作には良く合っています。
『連尺』は背負子の紐。Webで検索するとその意味は出ますが、語源がわからりません。“尺”が30cm前後の長さの単位であるとしたら、背負子紐が身体に密着する肩当ての太い部分がそれにあたります。正面から見て並んだその姿が連なっているところから付けた名前なのでしょうか。演目の内容は、新しい市(いち)が立つことを聞いた商売人が、永代の権利欲しさで一番最初に店を出そうと争う話です。女の歌賃(餅のこと。搗ち飯)売りと男の絹布売りが、口喧嘩から歌合戦、足押(すねを押し合う足相撲)、さらには相撲で決着を付けるという騒ぎになります。ところどころにセクハラめいた所作もある中、いずれも男が負けを認めないのは現代に通じます。明治以降、公序良俗に反するとして上演禁止になっていたものを当代又三郎師が復曲したそうです。
狂言は諷刺の芸。『光る君へ』でも、散楽が演じられたり、『白氏文集・新楽府』の諷諭が語られましたが、時代(とき)の権威に抗う姿勢は、豊穣な“対向文化”を育ててきたことの一つの象徴でもあります。
自壊する国のありよう ― 2024年06月15日 15:25

税収を私物化し、無駄な開発と中抜き利権に加え、裏金を作っては脱税を繰り返すような集団が野放しになっている一方、些細なミスで永住許可を取り消すような国が選ばれるはずがない。自壊に向けてまた一歩踏み出したようだ。日本語学習を支援するボランティアを続けて良くわかったことの一つは、例外はあるにせよ、母語以外の外国語を学ぶ人が使うその外国語は平均的な母語話者より“美しく”なるというものである。詭弁や忖度が蔓延する社会を反映することの少ないその“美しい”言葉を聞いていると、放浪の語り芸に耳を傾け伝統文化を育み続けてきたこの国の姿を、彼らにこそ、より多く知ってもらいたいという気分になる。
ハイブリッド化する古典劇 ― 2024年06月24日 15:28
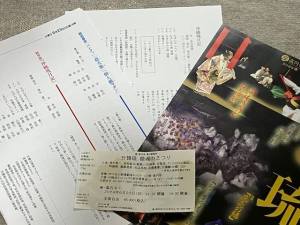
6年ぶりの「座・高円寺」。前回は劇団「態変」の『ニライカナイ』、その前はさらに5年遡り風琴工房の『国語の時間』でした。今回の『日韓琉 鎮魂の祭り』は、シテ方能楽師清水寬二さんを中心とした実行委員会が主催し、故多田富雄氏の新作能『沖縄残月記』・『望恨歌』に加え、韓国と沖縄の伝統芸能を組み合わせた4日間連続の公演です。その最終日を観てきました。
演目は第一部が韓国の農楽から『パンクッ』と『農夫歌』。パンクッは韓国語で판굿、放浪の芸人たちが農村を巡っては村々で豊作を予祝する音楽の一つ。太平簫(テピョンソ:管楽器)の“一声”から始まる集団演奏の音楽は、本来は戸外で行われるものだけに、会場をその世界一色に染め上げてしまう豪快さがあります。一方で、その様子には、儺戯(なぎ:追儺、鬼遣らい)から能へとつながる東アジアの伝統芸能の流れを感じさせるのです。その農楽に歌が入ったものが農夫歌。パンソリの唄者(ソリックン)である安聖民さんの声ならではの迫力で、強く豊かに響きます。
第二部は能『沖縄残月記』。太平洋戦争末期の沖縄戦の戦禍を題材にした作品です。壺屋の陶工の息子が風車を手にしたことでマブイ(魂)を落とし、ユタの言葉のままに親子で浦添の森へ向かうと、清明節の月夜の晩に曾祖母の霊に出会います。その“大ばんば”カマドが子供を亡くした沖縄地上戦での有様を縷々(るる)語るのです。演目全体に沖縄の伝統歌謡が散りばめられ、沖縄語の詞章が多いシテツレ(陶工)は能楽師ではなく沖縄音楽の演者になりました。二日目に演じられた同じ演目より、多くの演出を加えた「ウチナーバージョン」とも言える取り組みの成果なのです。
たとえば、天籟能の同人である槻宅(つちたく)聡さんの笛“一声”がある一方で、琉球笛で始まる場面も配されており、能と沖縄伝統劇が渾然一体となった新しい演劇の創造に立ち会った心持ちがしました。多田さんの創作に新たな光芒(それは太陽の子:テダノファかもしれません)を射した演出は、この作品が古典劇として残る上での大きな意味付けを示したように思います。沖縄での再々演が遠からず行われるものでしょう。
公演の最後は、高円寺ならではの特別ゲスト阿波踊りの「ひょっとこ連」も登場し、日韓琉フェスティバルの打ち上げに相応しいエンディングで締められましたが、後刻聞いた話によれば、それは関係者の宴席で隣り合わせた縁から生まれた企画だったようです。東アジアの芸能がこれからも様々なカタチで縁をつなぐ場に参加していければと考えています。
演目は第一部が韓国の農楽から『パンクッ』と『農夫歌』。パンクッは韓国語で판굿、放浪の芸人たちが農村を巡っては村々で豊作を予祝する音楽の一つ。太平簫(テピョンソ:管楽器)の“一声”から始まる集団演奏の音楽は、本来は戸外で行われるものだけに、会場をその世界一色に染め上げてしまう豪快さがあります。一方で、その様子には、儺戯(なぎ:追儺、鬼遣らい)から能へとつながる東アジアの伝統芸能の流れを感じさせるのです。その農楽に歌が入ったものが農夫歌。パンソリの唄者(ソリックン)である安聖民さんの声ならではの迫力で、強く豊かに響きます。
第二部は能『沖縄残月記』。太平洋戦争末期の沖縄戦の戦禍を題材にした作品です。壺屋の陶工の息子が風車を手にしたことでマブイ(魂)を落とし、ユタの言葉のままに親子で浦添の森へ向かうと、清明節の月夜の晩に曾祖母の霊に出会います。その“大ばんば”カマドが子供を亡くした沖縄地上戦での有様を縷々(るる)語るのです。演目全体に沖縄の伝統歌謡が散りばめられ、沖縄語の詞章が多いシテツレ(陶工)は能楽師ではなく沖縄音楽の演者になりました。二日目に演じられた同じ演目より、多くの演出を加えた「ウチナーバージョン」とも言える取り組みの成果なのです。
たとえば、天籟能の同人である槻宅(つちたく)聡さんの笛“一声”がある一方で、琉球笛で始まる場面も配されており、能と沖縄伝統劇が渾然一体となった新しい演劇の創造に立ち会った心持ちがしました。多田さんの創作に新たな光芒(それは太陽の子:テダノファかもしれません)を射した演出は、この作品が古典劇として残る上での大きな意味付けを示したように思います。沖縄での再々演が遠からず行われるものでしょう。
公演の最後は、高円寺ならではの特別ゲスト阿波踊りの「ひょっとこ連」も登場し、日韓琉フェスティバルの打ち上げに相応しいエンディングで締められましたが、後刻聞いた話によれば、それは関係者の宴席で隣り合わせた縁から生まれた企画だったようです。東アジアの芸能がこれからも様々なカタチで縁をつなぐ場に参加していければと考えています。