国際紛争の現場に関わるボランティア ― 2024年10月04日 16:42

恒例となっているMSFへの寄付。今年もまた、世界中で起きている紛争の各所に赴いている人々がいることを想う。犠牲となった方に合掌。
電通毎日劇場『総裁選』 ― 2024年10月05日 16:47
2週間以上に渡って連日メディアが報じ続けた“総裁選”なるものは、電通が仕掛けたただの茶番劇だったことが明らかになりました。世評を味方につけて優柔不断な無派閥票を取り込もうと石破候補が発した数々の政策は、「舌の根」も乾かないうちにあっさりと覆されています。
子供の頃から批判精神を養われることなく上位下達に飼い慣らされた多くの国民が、次の選挙でどのような行動を示す事になるのかに、正直なところ関心はありません。“政治不信”などと言いながら、そもそも「政治」そのものより「政局」への関心ばかりが高いだけの消費者マインドがそう簡単に変わるとも思いませんから…。
留学生への日本語学習支援や、日本語教室でのボランティアで意識してきたことの一つは、選挙権のない彼らがこの国で住み続ける時に重要な自分の言葉を持つ必要性です。この先、どのようなことがあっても自分自身の言葉で考えることが外国人である彼らには何より死活問題だと思うからです。繰り返し短い文章を書いてもらって、それを添削し「例」として示す。正解などありません。どのような話題であっても彼ら自身の言葉で語られてこそ意味があります。
そしてこの国が、アジアの中で今もなお優位性を保っている数少ないアドバンテージの一つが、独裁的な政治体制下に置かれることなく積み重ねられてきた人文科学の成果ではないのかと考えています。それがいつまで保つかは分かりませんが、彼らと一緒に学び続けたいと改めて考え直した69歳の誕生日です。
子供の頃から批判精神を養われることなく上位下達に飼い慣らされた多くの国民が、次の選挙でどのような行動を示す事になるのかに、正直なところ関心はありません。“政治不信”などと言いながら、そもそも「政治」そのものより「政局」への関心ばかりが高いだけの消費者マインドがそう簡単に変わるとも思いませんから…。
留学生への日本語学習支援や、日本語教室でのボランティアで意識してきたことの一つは、選挙権のない彼らがこの国で住み続ける時に重要な自分の言葉を持つ必要性です。この先、どのようなことがあっても自分自身の言葉で考えることが外国人である彼らには何より死活問題だと思うからです。繰り返し短い文章を書いてもらって、それを添削し「例」として示す。正解などありません。どのような話題であっても彼ら自身の言葉で語られてこそ意味があります。
そしてこの国が、アジアの中で今もなお優位性を保っている数少ないアドバンテージの一つが、独裁的な政治体制下に置かれることなく積み重ねられてきた人文科学の成果ではないのかと考えています。それがいつまで保つかは分かりませんが、彼らと一緒に学び続けたいと改めて考え直した69歳の誕生日です。
オーラルヒストリーとしての作文朗読 ― 2024年10月07日 16:50

ようやく暑さが峠を越したかと思われる昨今ですが、昨日は用があって横浜港の近くまで足を伸ばしました。前回の横浜市長選挙で争点となった山下埠頭へのIR誘致が中止となった後、再開発計画へ市民の声を届けようとする実行委員会の中に、横浜ボートシアターのメンバーが参加していて、船、正確には「艀(はしけ)」を舞台とする劇団ならではの新しい問題提起が企画されたのです。内容は艀の概要と生活史を辿る講演なのですが、劇団ならではのユニークな試みがありました。
戦後、高度成長に伴う物流の増加で活躍した横浜港の艀は、急速に数を増して港周辺の川沿いにも多数係留されましたが、徐々に大型のコンテナ船や荷揚げクレーンに置き換わり、今では埠頭周辺の一部に残るだけです。しかし、当時は職住一体となったその空間に多くの水上生活者が存在し、仕事に沿って東京湾を移動した関係で、彼らの子供たちは「水上学校」という寄宿舎付きの学校に通い、週末だけ艀に帰るような暮らしをしていました。その生活の記録が、戦後の一時期に全国へ拡がった綴り方運動のもとで、作文として文集に残っていたのです。
講演は、運河史研究の河北氏が歴史の概要を述べた後、前述の作文を一次資料として研究している横浜市発展記念館の松本氏が、その背景と個々の作文から読み取れる艀の生活を解説したのですが、その際、文章の紹介は、文字ではなく、横浜ボートシアターの舞台公演にも参加している演者が語ったのです。文集に残る作文は、いずれも“高評価”というフィルターのかかったものではありますが、読み上げられることで、公的文書などには残らない生活の一面を立体的に浮かび上がらせました。一種のオーラルヒストリーの再現とも呼べるような仕掛けです。
この「艀」講演はシリーズ化が予定されていますが、副題の通り、貨物ならぬ文化を運び、現代を“つなぐ”艀になりそうです。
戦後、高度成長に伴う物流の増加で活躍した横浜港の艀は、急速に数を増して港周辺の川沿いにも多数係留されましたが、徐々に大型のコンテナ船や荷揚げクレーンに置き換わり、今では埠頭周辺の一部に残るだけです。しかし、当時は職住一体となったその空間に多くの水上生活者が存在し、仕事に沿って東京湾を移動した関係で、彼らの子供たちは「水上学校」という寄宿舎付きの学校に通い、週末だけ艀に帰るような暮らしをしていました。その生活の記録が、戦後の一時期に全国へ拡がった綴り方運動のもとで、作文として文集に残っていたのです。
講演は、運河史研究の河北氏が歴史の概要を述べた後、前述の作文を一次資料として研究している横浜市発展記念館の松本氏が、その背景と個々の作文から読み取れる艀の生活を解説したのですが、その際、文章の紹介は、文字ではなく、横浜ボートシアターの舞台公演にも参加している演者が語ったのです。文集に残る作文は、いずれも“高評価”というフィルターのかかったものではありますが、読み上げられることで、公的文書などには残らない生活の一面を立体的に浮かび上がらせました。一種のオーラルヒストリーの再現とも呼べるような仕掛けです。
この「艀」講演はシリーズ化が予定されていますが、副題の通り、貨物ならぬ文化を運び、現代を“つなぐ”艀になりそうです。
護摩としての芸能 ― 2024年10月13日 16:56

青物横丁という地名は随分と前から知っていたように思いますが行ったのは昨日が初めてです。京浜急行の駅が最寄りにあっても、私は東急沿線の住人なので大井町へ出て、そこから歩きました。徒歩で15分離れた場所は、鉄道の乗換案内には候補として出てきませんが、ネットの地図で見ればさほど遠くないことが一見してわかります。定期券を使わなくなると同時に、地図をよく眺めるようになった変化は、街歩きという別の楽しみを教えてくれました。
さて、訪ねたのは青物横丁駅から至近の海雲寺というお寺です。三宝荒神の竈(かまど)神を祀っているところから、江戸時代以来町火消(まちびけ)しの信仰を集めており、護摩堂の天井にはその各組を象徴する纏(まとい)図なども描かれています。この一帯が品川宿でもあったところから、他にも様々な由緒があるのですが、その中に、寄席芸人からの奉納舞台が多く開かれたことが挙げられます。例えば、浪曲では二代目廣澤虎造、初代木村重松という大名跡もここで浪花節を唸(うな)りました。
昨日は、その再現とでもいうような浪曲の公演があり初めて訪ねたという次第です。演者は玉川奈々福(「鹿島の棒祭」•「椿太夫の恋」)、広沢菊春(「新門と梅ヶ谷」)、前読みの天中軒かおり(「若き日の小村寿太郎」)の三人で四席。いずれも浪曲らしい演目です。護摩堂の中に設(しつらえ)られたテーブル掛けを前に、当寺和尚さんの“短い”護摩焚(ごまた)き儀式による幕開けも行われました。
お菰(こも)さんに扮した新門辰五郎が見立てた相撲取り梅ヶ谷の話は、人は見かけによらないという時代物の定番とも言える筋ですが、菊春さんの虎造ばりに少し濁声(ダミごえ)が入った声調が良く合っていました。奈々福さんはいつもながらの見事な“唸り”と“目線”を披露してくれますが、今回はそれ以上に、演目それぞれに出てくる女性の“声色”の出し分けの見事さにちょっと震えました。甘酒屋に入ってくる白髪の老婆、女郎屋の遣手ばばあ、花魁椿太夫の三者三様が眼前にありありと浮かぶのです。喩えていえば、伝統芸能の世界に一人芝居が混淆したような新しい世界を見ているようでした。いずれも過去に聴いた話であるにも関わらずです。
さて、訪ねたのは青物横丁駅から至近の海雲寺というお寺です。三宝荒神の竈(かまど)神を祀っているところから、江戸時代以来町火消(まちびけ)しの信仰を集めており、護摩堂の天井にはその各組を象徴する纏(まとい)図なども描かれています。この一帯が品川宿でもあったところから、他にも様々な由緒があるのですが、その中に、寄席芸人からの奉納舞台が多く開かれたことが挙げられます。例えば、浪曲では二代目廣澤虎造、初代木村重松という大名跡もここで浪花節を唸(うな)りました。
昨日は、その再現とでもいうような浪曲の公演があり初めて訪ねたという次第です。演者は玉川奈々福(「鹿島の棒祭」•「椿太夫の恋」)、広沢菊春(「新門と梅ヶ谷」)、前読みの天中軒かおり(「若き日の小村寿太郎」)の三人で四席。いずれも浪曲らしい演目です。護摩堂の中に設(しつらえ)られたテーブル掛けを前に、当寺和尚さんの“短い”護摩焚(ごまた)き儀式による幕開けも行われました。
お菰(こも)さんに扮した新門辰五郎が見立てた相撲取り梅ヶ谷の話は、人は見かけによらないという時代物の定番とも言える筋ですが、菊春さんの虎造ばりに少し濁声(ダミごえ)が入った声調が良く合っていました。奈々福さんはいつもながらの見事な“唸り”と“目線”を披露してくれますが、今回はそれ以上に、演目それぞれに出てくる女性の“声色”の出し分けの見事さにちょっと震えました。甘酒屋に入ってくる白髪の老婆、女郎屋の遣手ばばあ、花魁椿太夫の三者三様が眼前にありありと浮かぶのです。喩えていえば、伝統芸能の世界に一人芝居が混淆したような新しい世界を見ているようでした。いずれも過去に聴いた話であるにも関わらずです。
人間としての行いを問い続けてきた人々 ― 2024年10月15日 16:58
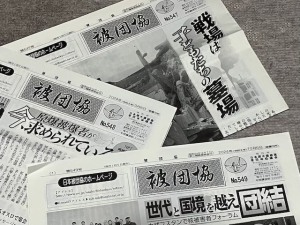
“核共有”も視野に入れる新しい日米安保の体制を検討する石破政権の発足と合わせたかのように、「日本被団協」へノーベル平和賞が授与されるという発表がありました。
1955年、前年のビキニ環礁水爆実験で被曝した第五福竜丸の事件もあって全国で3000万を超える原水爆禁止の署名が集まりました。それを受けるように開かれた世界大会で、被爆者代表として発言し、後に政党の思惑で分裂した運動に幻滅しながらも、広島を訪れる子どもたちに向けて被爆体験を語り続けた高橋昭博さんという人がいます。
翌年に発足した広島県原爆被害者協議会に参加し、後に拡がった全国組織「日本被団協」でも活動する一方、広島市の広報課に職員として務め、79年からの4年間は広島平和記念資料館の館長でした。私が20代の後半に初めて訪ねた広島でお会いして以来、手紙の遣り取りも含め、いつも“草の根”という言葉を体現する生き方をしていた方だと敬っていました。
「被団協」の運動はいつもそうした“草の根”の人たちに支えられてきたものです。そこには、あの悲劇から残った者として、一人でも続けるという強い意志が感じ取れます。今回の受賞を受けて代表委員の箕牧さんが「ガザでの紛争で傷ついた子どもたちと、原爆孤児の姿が重なる」と語ったことがとても印象的でした。政治問題以前の、人間としての行いそのものを問い続けている人だからこそのメッセージだったのでしょう。
1955年、前年のビキニ環礁水爆実験で被曝した第五福竜丸の事件もあって全国で3000万を超える原水爆禁止の署名が集まりました。それを受けるように開かれた世界大会で、被爆者代表として発言し、後に政党の思惑で分裂した運動に幻滅しながらも、広島を訪れる子どもたちに向けて被爆体験を語り続けた高橋昭博さんという人がいます。
翌年に発足した広島県原爆被害者協議会に参加し、後に拡がった全国組織「日本被団協」でも活動する一方、広島市の広報課に職員として務め、79年からの4年間は広島平和記念資料館の館長でした。私が20代の後半に初めて訪ねた広島でお会いして以来、手紙の遣り取りも含め、いつも“草の根”という言葉を体現する生き方をしていた方だと敬っていました。
「被団協」の運動はいつもそうした“草の根”の人たちに支えられてきたものです。そこには、あの悲劇から残った者として、一人でも続けるという強い意志が感じ取れます。今回の受賞を受けて代表委員の箕牧さんが「ガザでの紛争で傷ついた子どもたちと、原爆孤児の姿が重なる」と語ったことがとても印象的でした。政治問題以前の、人間としての行いそのものを問い続けている人だからこそのメッセージだったのでしょう。