鎮魂から生まれる芸能 ― 2024年05月26日 15:16

地元の国際交流ラウンジで新しい学習者を担当することになりました。中国・ベトナムに続いてマレーシア出身の社会人です。この日本が、圧倒的に被害ばかりの戦争体験を伝えてきたのとは反対に、アジアの他国では若者に戦前日本の加害行為が教えられてきました。その延長線上に、あえて日本語を学ぼうとするアジアの若い人たちがいて、私は日本語の母語話者としてできる範囲のことを伝えてきたつもりです。
自壊へと進んでいるこの国では、伝統文化の継承も困難になりつつありますが、源氏物語を研究しているという留学生と会って話せば、アーサー・ウェイリーのような先人を継ぐ若い外国人研究者によっても未来の世界へ伝えられる豊かな文化鉱脈が、この国にはまだ豊富に残っているという認識を新たにします。
昨日、東大駒場キャンパスへ足を運んだのも、それを深めるためだと言えるでしょうか。「韓国・日本・琉球の伝統芸能と現代社会」と題された講演会は20人弱の対面参加者とオンラインで参加した関係者によって開かれました。これは、6月20〜23日に高円寺で開かれる「鎮魂のまつり」の関連イベントで、東アジアの伝統芸能が混淆してきた歴史を振り返りながら、戦争で失われた多くの命の鎮魂を、慰霊につながる各地の伝統芸能によって行おうという公演の事前学習会のようなものです。
公演そのものは、多田富雄の新作能『望恨歌』・『沖縄残月記』を中心に、韓国の農楽・パンソリ、琉球舞踊・組踊りなどを組み合わせて構成されるもので、基調講演は、長年アジアの芸術家との交流を進め、上記演目のシテ方も勤め、今回の公演を企画した清水寬二さんが行いました。シンガポールに始まり、戦前日本軍が侵してきた各地での伝統芸能者との交流には様々な困難もあったようですが、そこから得られた人の繋がりが、今このような公演に結実したとも言えるのでしょう。
他にも伝統芸能に関わる多くの研究報告が行われ、素人にはやや敷居が高いところもありましたが、遠出したかいがあって、多くの示唆を得ることができました。
自壊へと進んでいるこの国では、伝統文化の継承も困難になりつつありますが、源氏物語を研究しているという留学生と会って話せば、アーサー・ウェイリーのような先人を継ぐ若い外国人研究者によっても未来の世界へ伝えられる豊かな文化鉱脈が、この国にはまだ豊富に残っているという認識を新たにします。
昨日、東大駒場キャンパスへ足を運んだのも、それを深めるためだと言えるでしょうか。「韓国・日本・琉球の伝統芸能と現代社会」と題された講演会は20人弱の対面参加者とオンラインで参加した関係者によって開かれました。これは、6月20〜23日に高円寺で開かれる「鎮魂のまつり」の関連イベントで、東アジアの伝統芸能が混淆してきた歴史を振り返りながら、戦争で失われた多くの命の鎮魂を、慰霊につながる各地の伝統芸能によって行おうという公演の事前学習会のようなものです。
公演そのものは、多田富雄の新作能『望恨歌』・『沖縄残月記』を中心に、韓国の農楽・パンソリ、琉球舞踊・組踊りなどを組み合わせて構成されるもので、基調講演は、長年アジアの芸術家との交流を進め、上記演目のシテ方も勤め、今回の公演を企画した清水寬二さんが行いました。シンガポールに始まり、戦前日本軍が侵してきた各地での伝統芸能者との交流には様々な困難もあったようですが、そこから得られた人の繋がりが、今このような公演に結実したとも言えるのでしょう。
他にも伝統芸能に関わる多くの研究報告が行われ、素人にはやや敷居が高いところもありましたが、遠出したかいがあって、多くの示唆を得ることができました。
民に選ばれない国のありよう ― 2024年05月27日 15:19
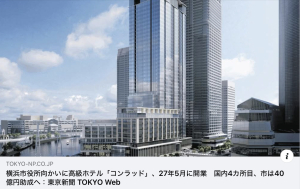
「市は、企業立地促進条例に基づき、国際競争力強化を図るホテル事業に対し、40億円を助成する方向」だそうだが、思わず企業リッチと読んでしまった。それにしても何の競争力なのだろうか。一般の留学生や外国人労働者に“選ばれない”国になりつつある状況に対し、何らかの助成を行うつもりはないのだろうか。