Clubhouseで伝統芸能の話を聴く ― 2021年09月15日 19:18
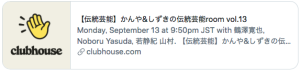
音声のSNSと言うのだろか。「Clubhouse」の“アプリ”を初めて使ってみた。これまで、ほとんど関心が無かったのだが、今年の8月に招待制から一般に開放されたことを知って、ある「ルーム」で話される内容を是非聴いてみたいというラジオリスナーのような単純な動機からスマホにインストールした。
何度か口演を聴いたことがある女流義太夫の鶴澤寛也さんと上方舞の山村若静紀さんが開いている「かんや&しずきの伝統芸能room」という“ルーム”に、能楽師の安田登さんがゲストに出るとTwitterで知り、一昨日午後9時の開始時間前に食事を済ませ、定刻を過ぎていたものの何とか無事に参加することができた。事前の断りもなく参加するのに若干の躊躇もなくはなかったが、興味の方が勝ってしまった。
冒頭、宝塚歌劇で最近上演された楠木正行(まさつら)三兄弟が主役の「桜嵐記」の話があったようで、そこは聴けなかったが、フランス人の古代中国研究者マルセル・グラネの言葉「王朝の舞踊は音楽と身振りによる紋章のようなもの」から始まった芸能の身体性に関わる話が大変面白かった。以下に心覚えのメモを残す(誤解があるかも)。
ヘブライ語による聖書が近世に復活できたのは、そこに歌うための旋律が施されていたからで、たとえ民族が一次的に消滅しても、舞踊と音楽さえ残っていれば復活できる可能性は高い。日本の伝統芸能に含まれているものが、失われた文化を取り戻すカギになる。
世阿弥以降、様々に変化した芸能にも、時代を超えて変わらない身体性がある。舞の型などはその象徴。ただ、正座や立ち座りを含め日常の歩き方から体型までもがすっかり変わってしまった現状では工夫が必要。伝統芸能の玄人から見た“なんちゃって芸”への不安。西洋音楽など決められた形式からの影響もある。
どこまで観客に合わせるか。能は意識しない。義太夫は近松ブームが大きな変節点。文学の影響もある。『曾根崎心中』が新作みたいに思えるところも。
そもそも舞は興行として成り立たない。人口減の中、稽古事として型が守られている。鏡稽古(お師匠さんの踊りを鏡のように真似する)がうまくできない。素直に真似ることができなくなっている。頭の使いすぎ。それまでの時代に存在しなかった新たな職業人に芸能を教える。新しい視点に気づく機会。過去を真似るのではなく新しいイノベーションが必要。現代はその生まれ変わる時代。
オンラインもただ配信するところから、新しいテクノロジーとの融合など幅広い可能性を探る動きが出てきた。アンケートで選ばれた商業ベースの演目ばかりになりがち。復曲を行う余裕がない。下がったハードルで融合せず、海外にきちんと見せるための仕組み作りが大事。
芸能そのものではないが、留学生を含む外国人への学習支援の中で、日本語に含まれる豊穣な文化の、特に伝統芸能が持つ“音楽性”には以前から強い関心がある。
何度か口演を聴いたことがある女流義太夫の鶴澤寛也さんと上方舞の山村若静紀さんが開いている「かんや&しずきの伝統芸能room」という“ルーム”に、能楽師の安田登さんがゲストに出るとTwitterで知り、一昨日午後9時の開始時間前に食事を済ませ、定刻を過ぎていたものの何とか無事に参加することができた。事前の断りもなく参加するのに若干の躊躇もなくはなかったが、興味の方が勝ってしまった。
冒頭、宝塚歌劇で最近上演された楠木正行(まさつら)三兄弟が主役の「桜嵐記」の話があったようで、そこは聴けなかったが、フランス人の古代中国研究者マルセル・グラネの言葉「王朝の舞踊は音楽と身振りによる紋章のようなもの」から始まった芸能の身体性に関わる話が大変面白かった。以下に心覚えのメモを残す(誤解があるかも)。
ヘブライ語による聖書が近世に復活できたのは、そこに歌うための旋律が施されていたからで、たとえ民族が一次的に消滅しても、舞踊と音楽さえ残っていれば復活できる可能性は高い。日本の伝統芸能に含まれているものが、失われた文化を取り戻すカギになる。
世阿弥以降、様々に変化した芸能にも、時代を超えて変わらない身体性がある。舞の型などはその象徴。ただ、正座や立ち座りを含め日常の歩き方から体型までもがすっかり変わってしまった現状では工夫が必要。伝統芸能の玄人から見た“なんちゃって芸”への不安。西洋音楽など決められた形式からの影響もある。
どこまで観客に合わせるか。能は意識しない。義太夫は近松ブームが大きな変節点。文学の影響もある。『曾根崎心中』が新作みたいに思えるところも。
そもそも舞は興行として成り立たない。人口減の中、稽古事として型が守られている。鏡稽古(お師匠さんの踊りを鏡のように真似する)がうまくできない。素直に真似ることができなくなっている。頭の使いすぎ。それまでの時代に存在しなかった新たな職業人に芸能を教える。新しい視点に気づく機会。過去を真似るのではなく新しいイノベーションが必要。現代はその生まれ変わる時代。
オンラインもただ配信するところから、新しいテクノロジーとの融合など幅広い可能性を探る動きが出てきた。アンケートで選ばれた商業ベースの演目ばかりになりがち。復曲を行う余裕がない。下がったハードルで融合せず、海外にきちんと見せるための仕組み作りが大事。
芸能そのものではないが、留学生を含む外国人への学習支援の中で、日本語に含まれる豊穣な文化の、特に伝統芸能が持つ“音楽性”には以前から強い関心がある。