人形を活かす芸 ― 2017年08月16日 18:55
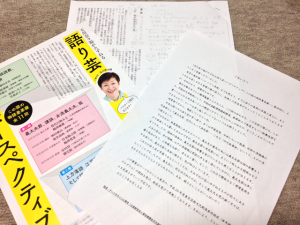
「話り芸パースペクティブ」の4回目。今回は義太夫節。この“語り芸”を生で聴くのも初めてだが、60名定員の狭い和室で演者を目の前にして聴いたことそのものが二度とない機会になったかもしれない。
文楽つまり人形浄瑠璃の“語り”でもある義太夫節を、太夫と三味線だけで行うのを素浄瑠璃という。人形遣いも含めた通常の文楽公演と同じ規模の劇場で行われることもあるこの“語り”を聴いていて、何と言ったら良いのだろうか。ただただ圧倒された。伝統芸能に関して全く素人である私のような者でも、繰り広げられている光景が凄まじいものであることだけは良くわかる。“目一杯”という言葉があるが、この日の演者の姿にはそれを深く納得させるものがあった。
演じる場所が変わっても“語り”そのものは全く変わらない。そこには、演じる者と観る者の間にはっきりとした一線を引き、観る者に対して、これが“芸能者”だという完成形を示すような意気込みを感じさせる。当然、そこには緊張感が生まれる。喉をつぶしてこそ、そこを超える“語り”が生まれるように、極限を見せてこそ“演者”であることが認められる世界でもある。太夫と三味線は切っ先を交える真剣勝負そのままに、相手の“息”を測りながら物語世界を創り出す。床本(太夫が舞台に持ち込む浄瑠璃台本)に書いてある言葉を違えることはないが、その一言一言に命が吹き込まれる。三味線が相呼応する。
だからこそ、舞台の人形が“生きる”のだ。私は文楽の生の公演を観たことはないので、義太夫節を聴いて人形の動きを想像することはできないが、彼ら演者にとっては、それがあってこその“語り”なのだろう。文楽が非常に保守的な世界と思われ、時に厭われることの理由には、人形を“活かす”芸として絶対に譲れない一線があるからではないだろうか。“語り”の芸ではあるけれど、唾も汗も飛び散らせ呻吟する様はアスリートにも似る。太夫と三味線を交互に見ていて、さながら並走するランナーを思い浮かべることがあった。彼らはゴールラインを越して倒れ込むことはなかったが・・・。
文楽つまり人形浄瑠璃の“語り”でもある義太夫節を、太夫と三味線だけで行うのを素浄瑠璃という。人形遣いも含めた通常の文楽公演と同じ規模の劇場で行われることもあるこの“語り”を聴いていて、何と言ったら良いのだろうか。ただただ圧倒された。伝統芸能に関して全く素人である私のような者でも、繰り広げられている光景が凄まじいものであることだけは良くわかる。“目一杯”という言葉があるが、この日の演者の姿にはそれを深く納得させるものがあった。
演じる場所が変わっても“語り”そのものは全く変わらない。そこには、演じる者と観る者の間にはっきりとした一線を引き、観る者に対して、これが“芸能者”だという完成形を示すような意気込みを感じさせる。当然、そこには緊張感が生まれる。喉をつぶしてこそ、そこを超える“語り”が生まれるように、極限を見せてこそ“演者”であることが認められる世界でもある。太夫と三味線は切っ先を交える真剣勝負そのままに、相手の“息”を測りながら物語世界を創り出す。床本(太夫が舞台に持ち込む浄瑠璃台本)に書いてある言葉を違えることはないが、その一言一言に命が吹き込まれる。三味線が相呼応する。
だからこそ、舞台の人形が“生きる”のだ。私は文楽の生の公演を観たことはないので、義太夫節を聴いて人形の動きを想像することはできないが、彼ら演者にとっては、それがあってこその“語り”なのだろう。文楽が非常に保守的な世界と思われ、時に厭われることの理由には、人形を“活かす”芸として絶対に譲れない一線があるからではないだろうか。“語り”の芸ではあるけれど、唾も汗も飛び散らせ呻吟する様はアスリートにも似る。太夫と三味線を交互に見ていて、さながら並走するランナーを思い浮かべることがあった。彼らはゴールラインを越して倒れ込むことはなかったが・・・。